
マネーの公理って有名な本。
短時間でサッと読みたいなぁ
この記事では、投資の名著として知られる「マネーの公理」を要約した記事となります。
マネーの公理の結論としては、「金持ちになるには、多少のリスクを背負う必要がある」です。
この記事でわかること
- 金持ちになるための教え 『チューリッヒの12の公理』
- 時短のため、大事なところをギュッとまとめた要点を箇条書きで紹介
- 「マネーの公理」の「よい点」「悪い点」の紹介
この記事の信頼性
筆者 マックス・ギュンターってどんな人?
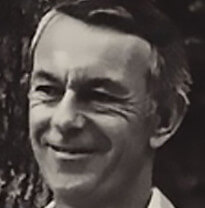
- スイスの投資家
- スイス銀行界で有名な金融マフィア「チューリッヒの小鬼」の一人を父に持つ
- 13歳で株式マーケットに参入。財を成す
チューリッヒの公理とは?
- スイスで生まれた、お金に関するリスク、マネジメントに関する教え
- リスクをとって賭けをする、あらゆる状況に対応できる教え
- スイス人投機家クラブで暗黙のうちに生まれた教えを、後に12にまとめる。わかりやすく成文化
この記事を書いた人

✔ 株式投資歴10年
✔ 国内外個別株、インデックス投資
✔ 投資関連本は山ほど読んで勉強しています!
12の教えを、箇条書きに要約し、「わかりやすく」まとめました。
Contents
要約

「マネーの公理」は、「もくじを読めば、おおよそのことが分かる」と言われます。
各章を、サッと目を通せるように
・ 目次の部分を「冒頭の文章」
・ 内容は箇条書き
で構成しました。
マネーの公理の全体像は、こんな感じです。
マネーの公理 12の教え まとめ
- 心配は病気ではなく、健康の証である。もし、心配なことがないなら、十分なリスクをとっていないということだ
- 常に、早すぎるほど早く利食え
- 船が沈みはじめたら、祈るな。飛び込め。
- 人間の行動は予測できない。誰であれ、未来がわかると言う人を、たとえわずかでも信じてはいけない。
- カオスは、それが整然と見え始めない限り、危険ではない
- 根を下ろしてはいけない。それは、動きを鈍らせる
- 直観は、説明できるのであれば信頼できる
- 宇宙に関する神の計画には、あなたを金持ちにすることは含まれていないようだ
- 楽観は、最高を期待することを意味するが、自信は、最悪の場合にどのように対処するか知っていることを意味する。ただ単に楽観的というだけで行動してはならない。
- 大多数派の意見は無視しろ。それはおそらく間違っている。
- もし最初にうまくいかなければ、忘れろ
- 長期計画は、将来を管理できるという危険な確信を引き起こす。決して重きを置かないことが重要だ。
以下、それぞれの教えを要約していきます。
はじめに
本書は、賭けて勝つための本である。
本書で紹介するマネーについての約束事「チューリッヒの公理」という。
「チューリッヒの公理」は、すべてリスクとそのマネジメントに関するものである。
また、「チューリッヒの公理」は、より多くのお金を得るためにリスクをとって賭けをする、あらゆる状況に応用できる。
世界で最も賢い投資家、投機家となったスイス人。
スイス人は、人生を賢明に生きる方法は、リスクを回避することではない。
富や名声を得るためには、自分の所有物や精神的な満足感をリスクにさらさねければならないという結論に達した。
警告しておくが、「チューリッヒの公理」は最初に遭遇したときには、衝撃的である。
なぜなら、投資顧問のアドバイスのようなものとは全く異なるからだ。
「チューリッヒの公理」の価値は、
- 真実であるという確かな手ごたえ
- 第二、第三と重層的な深みを持ち、冷淡かつ実利的
- 投機の哲学だけでなく、人生の成功のみちしるべであること
銀行家であり、投機家でもあった父が、私に言った言葉
給与だけで考えるな。
給与だけでは決して金持ちになれない。
だから多くの人々が給与をもらって貧しくなるのだ。
自分のために、何かほかのものを持たなければならない。
お前に必要なのは「投機」だ。
第一の公理 リスクについて

心配は病気ではなく、健康の証である。
もし、心配なことがないなら、十分なリスクをとっていないということだ
・副公理Ⅰ:いつも意味のある勝負に出ること
・副公理Ⅱ:分散投資の誘惑に負けないこと
投機戦略(まとめ)
- お金をリスクにさらせ
- 少しくらい損することを恐れてはいけない
- チャンスに支払う代償は、「心配」という状態である
- 心配は、人生の熱くてピリッとしたスパイス
- (多少の心配しながら,投機を行うことに)一度慣れてしまえば、楽しむことができる
第二の公理 強欲について

常に、早すぎるほど早く利食え
・副公理Ⅲ:あらかじめ、投機からどれだけの利益がほしいのかを決めておけ。そして、それを手に入れたら、投機から手を引くのだ
投機戦略(まとめ)
- あらかじめ決めておいたゴールに達したら、手仕舞って、立ち去るべきだ
- もうしばらく勝ち続けることが、ほぼ確実ならば投機をやめなくてもよい
- 早すぎるほど早く利食う習慣になれるべきである
- 利食いした後、勝ちが続いていたとしても自分を責めないこと
- 早く利食いしなければ失っていた利益を守ることができた、と自分を慰めること
第三の公理 希望について

船が沈みはじめたら、祈るな。飛び込め。
・副公理Ⅳ:小さな損失は、人生の現実として甘んじて受けよ。大きな利益を待つ間には、何回かそういう経験をすると考えろ。
投機戦略(まとめ)
- 投機において問題が発生したら、うろたえずにすぐに立ち去れ
- 投機において、「期待」「祈り」は不要である
- 困難に陥ると人は感情に流されやすい。投機では、是が非でもそれを乗り越えるべき
- 損を納得して受け入れることを学ぶことは、絶対に必要な投機の技術である
- 優れた投機家が少ない理由、それは、困難時の感情を乗り越えたり、損を納得して受け入れることができないから
第四の公理 予測について

人間の行動は予測できない。
誰であれ、未来がわかると言う人を、たとえわずかでも信じてはいけない。
投機戦略(まとめ)
- 予測、予言に基づいた投機は行わないこと
- 「将来何が起こるか誰にも分からない」を肝に銘じること
- 「起こるだろう」という予測ではなく、「起こったこと」を基準に投機を行うこと
- 投資は、ある種の「予測」。失敗するときもある
- すべての預言者が、「うまくいく」と言ったが、うまくいかない投機。そのときは、素早く投機をやめること
第五の公理 パターンについて

カオスは、それが整然と見え始めない限り、危険ではない
・副公理Ⅴ:歴史家の罠に気をつけろ
・副公理Ⅵ:チャーティストの幻想に気をつけろ
・副公理Ⅶ:相関と因果関係の妄想に気をつけろ
・副公理Ⅷ:ギャンブラーの誤謬に気をつけろ
投機戦略(まとめ)
- 秩序が存在しないところに秩序を見つけるな
- 投機対象は徹底的に研究してから、投機をする
- 徹底的に研究しても、「全て知っている」とうぬぼれてはいけない
- 投資において、「幸運」という圧倒的に大きな存在を無視してはいけない
- 投機は、どんなに研究し勝率が上がっても、運悪く負けることもある。負けたら、すぐ投機から立ち去る用意をせよ
第六の公理 機動力について

根を下ろしてはいけない。
それは、動きを鈍らせる
・副公理Ⅸ:忠誠心やノスタルジーといった感情のせいで、下落相場に捕まってはいけない。
・副公理Ⅹ:より魅力的なものが見えたら、直ちに投資を中断しなければならない。
投機戦略(まとめ)
- 投機から投機へ移れるように、「機動力」を失わないようにする
- 投機対象に執着や、こだわりなどを持ちすぎてはいけない
- 1つの投機から、もう1つの投機へと簡単に跳ね回れということではない
- 投機は、勝算を慎重に評価して実行すること。つまらない理由で行動してはいけない
- 投機対象が明らかに価値を失いつつあり、明らかに見込みのある投機先が見つかれば動くこと
第七の公理 直観について

直観は、説明できるのであれば信頼できる
・副公理XI:直観と希望を混同するな
投機戦略(まとめ)
- 直観は、確実に信用できないものの、慎重かつ懐疑的に対処すれば、有効な投機ツールになりえる
- 直観は、不思議や空想的なことはない。どのように知ったか知ることなく、何か知っていること
- 強い直観がひらめいたとき、その直観を裏付ける自分の中の情報の保存場所が分かっていれば信頼せよ
- 強い直観がひらめいたとき、その直観を裏付ける証拠がないなら、その直観は無視するべき
- 直観は期待と混同されやすい。あなたが強く望む結果を約束するような直観には、特に注意が必要
第八の公理 宗教とオカルトについて

宇宙に関する神の計画には、あなたを金持ちにすることは含まれていないようだ
・副公理XII:もし、占星術が当たるのであれば、すべての占星術師は金持ちであろう
・副公理XIII:迷信は、追い払う必要はない。もし、適当な場所に置いておけば楽しめる。
投機戦略(まとめ)
- 公理は本質的に、お金とオカルトが組み合わされると、投機は突然うまくいかなくなると言っている
- 神はあなたの銀行口座に興味はなく、オカルト実践者が信仰者を金持ちにすることはない
- 神やオカルト、霊能力の助けを期待することは、役に立たないだけでなく、危険である
- 宗教、オカルトは、心配していない状態に落ち着かせるが、投機を行う上ではよくない状態(第1の公理 多少心配になるお金で投機せよ)
- 投機をするときは、頼れるのは自分だけ。自分自身の冷静な判断力に頼るのだ
第九の公理 楽観と悲観について

楽観は、最高を期待することを意味するが、自信は、最悪の場合にどのように対処するか知っていることを意味する。
ただ単に楽観的というだけで行動してはならない。
投機戦略(まとめ)
- 楽観主義は、投機家の敵である
- 公理は、単に楽観的になれるというだけでお金を賭けてはいけないと説く
- 物事が悪い方向に進んだ場合、自分をどう救うのか自問すべき。それがはっきりしているとき、あなたは自信をもっている状態である。
第十の公理 コンセンサスについて

大多数派の意見は無視しろ。
それはおそらく間違っている。
・副公理XIV:投機的流行を決して追うな。往々にして、何かを買う最高のときは、誰もそれを望まないときである。
投機戦略(まとめ)
- 大多数は、常に間違っているわけではないが、正しいことより間違っていることが多い
- 何も考えずに大多数に同意して、投機をしてはいけない。自分の頭であらゆることを考えること
- あなたにとって、最強の圧力は、「大多数と共に賭けさせようとする圧力」である
- 大多数と共に賭ける投機は、値段が高い時に買い、値段が安い時に売るという傾向を持つので、高い買い物となる
- 大多数と共に賭けることを避けるには、その存在と圧力を、鋭敏に認識すること
第十一の公理 執着について

もし最初にうまくいかなければ、忘れろ
・副公理XV 難平買いで悪い投資を何とかしようとするな
投機戦略(まとめ)
- 1つの投機対象から利益を絞り出そうとして、執着のワナに陥ってはならない
- こだわりの気持ちをもって投資をおいかけてはならない
- 難平買いは、悪い状況を改善できるように思える魅力を持つが、誤った考え方である
- 投資から利益のためだけに投資先を選ぶ自由を重視すること
- うまくいかない投資に執着することで、投資先を選ぶ自由を手放してはならない
第十二の公理 計画について
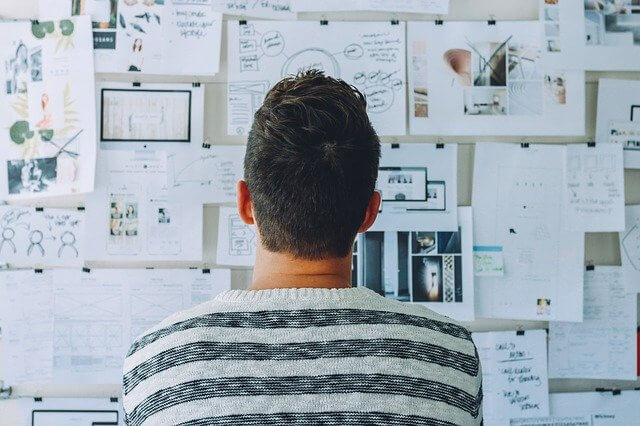
長期計画は、将来を管理できるという危険な確信を引き起こす。
決して重きを置かないことが重要だ。
・副公理XVI 長期投資を避けよ
投機戦略(まとめ)
- 公理は、自分の見ることのできない将来を計画する無益と危険に警告している
- 長期契約や長期投資に根をおろしてはいけない
- 好機が来たら、お金を投資。危険が来たら、撤退。何かが起きたときに反応すること、進退の自由を確保せよ
- 必要な長期資産計画は、ただ1つ。「金持ちになろうとする意志」だ
- 金持ちになる方法などない。あなたは、どうにかしてそれを成し遂げるしかない
書評
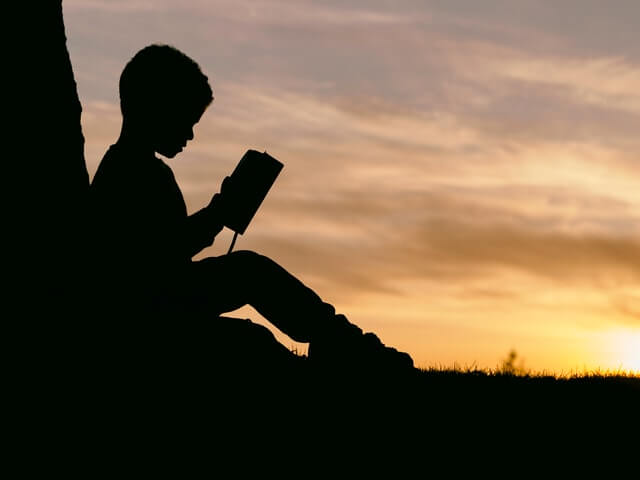
「よい点」「悪い点」を1つずつ挙げてみます。
【よい点】優れた「投資」の教科書であること
12の公理をざっとご覧いただくと、こんな印象を持ちます。
「イチかバチかのギャンブラーに向けて書かれたものではない」ということです。
なぜなら、本書では「過剰なリスクを取ること」や、「勝負に出ること」をすすめていません。
投資でも言われる、「適度なリスクを取れ」にとどまっています。
例えば、第1の公理 リスクについてでは、「少し」という言葉がついています。
・ 少し心配なくらいお金を賭けよ
・ 少しくらい損することを恐れるな
・ チャンスを得るための代償は「心配すること」
私は、株式投資は、「投機」、ギャンブルの部分は存在すると考えます。
なぜなら、
・ 短期や長期、どんなに上手な投資をしても、投資には「運」の要素があるから
・ どんなにリスクをそぎ落としていっても、投資には投機の部分はなくならないから
・ どんなにうまく言い表しても、投資と投機は明確に区別できないから
本文中には、こんな言葉があります。
投資と投機に違いはない。
すべての投資は投機である。
唯一の違いは、ある人はそれを認め、ある人はそれを認めないことだ。
「投資=善」 「投機=悪」
「自分がやっているのは『投資』。『投機』ではない!」
とよく言われます。
しかし、株式投資も、投機であると認めることで、この本の貴重な教えがスッと体に入ってきます。
多くの投資家を勝利に導き、スイス人を経済的に成功させた公理であることを忘れてはいけません。
若き日のウォーレン・バフェットは「競馬の達人」。
その相棒 チャーリー・マンガーは、「ポーカーの達人」。
投資の達人は、「投機」にも強いことは偶然ではありません。
結論としては、「投機の教科書」を頭から一度取っ払って、「投資の教科書」として読んでみようとなります。
【悪い点】すべての公理が手放しで賞賛できないこと
12番目の公理 「長期投資をするな」は、やはり違和感があります。
なぜなら、数々のデータからも、「長期投資は、短期投資よりリターンが高く、勝率も高い」ことは分かっているからです。
「長期投資を視野に入れずに、目の前で起きたことに対処していく」という本書の教え。
捉え方によっては「短期投資」を推奨しているように思えます。
ただ、もう少し踏み込んで考えてみる必要があります。
・ ガチガチな長期の計画にしばられるな。目の前に起きた現実も大切に
・ 自分は長期投資していると思考停止しないこと、投資に正解はない
・ 未来のことは分からない。あまりに長すぎる長期計画は不要
このように、公理を深堀してみて、ハッと気づくことがあります。
例えば、「S&P500」「オールカントリー(全世界対象)」インデックス投資。
私自身、「これやっとけば、とりあえず安心」と思考停止になっているところがあり、ハッとしました。
結論としては、「多少違和感がある公理でも、立ち止まって考えてみると、別の景色が見えてくる」ですね。
まとめ

この記事では、投資の名著として有名な「マネーの公理」の要約と書評をご紹介しました。
12の教えはどれも素晴らしい。
歯切れのよい教えが並ぶ一方で、「ドキッ」とさせられる教えもあります。
マネーの公理は、忘れたころに、何度も読み返して体に落とし込みたい教えばかり。
本記事では、ササっと短時間で復習がしやすいように、箇条書きに要約。
ぜひ利用していただければ、うれしいです。
多くの投資家が絶賛する、「マネーの公理」。
「王道」の投資本とは少し毛色の違う「マネーの公理」ですが、ぜひ読んでみてください。
