
「投資で一番大切な20の教え」って有名な本。
サクッと読める要約ないかな?
この記事は、「投資で一番大切な20の教え」という本の要約記事となります。
この記事でわかること
「投資で一番大切な20の教え」 第12章の要約から
・ マークス流 掘り出し物投資の解説
・ 掘り出し物の定義となぜ生まれるのか分かる
・ ハワードが警告する、掘り出し物投資
この記事の信頼性
「投資で一番大切な20の教え」 著者は ハワード・マークス

ウォーレン・バフェットも一目置く投資家として有名。
バフェットいわく、「ハワード・マークスからの顧客向けレターは、真っ先に読む」とのことです。
オークツリー・キャピタル・マネジメントの会長兼共同創業者
オークツリー・キャピタル・マネジメントは、ロサンゼルスを拠点とした投資会社で、運用資産は8000億ドル以上。
高利債投資や不良債権への投資を得意とする。
ウォートン・スクールにて金融を学び、シカゴ大学にてMBAを取得。
引用 アマゾン 商品紹介ページ 「投資で一番大切な20の教え」より
この記事を書いた人

✔ 株式投資歴10年
✔ 国内外個別株、インデックス投資
✔ 投資関連本は山ほど読んで勉強しています!
投資で勝つには、著名投資家の本で学ぶことが一番の早道です。
そこでこの記事では、「投資で一番大切な20の教え」を要約しました。
・ バフェットがこの本を大絶賛。
大量購入してバークシャーの株主総会で配布したから
・ 世間でも「名著」と名高いから
・ 私自身も読んでみて、稀に見る有益な投資本だと考えるから
※ ご参考までに、アマゾンでの評価は★4つ(387件)

「投資で一番大切な20の教え」を繰り返し読んでいる者としては、

詳しく要約したほうが、読者に有益なのでは?
と感じました。
ハワードの言葉や表現を大事にした要約を心がけました。
本記事をご覧いただければ、こんなメリットがあります。
・ ハワードが説く、掘り出し物投資の難しさ
・ 他の投資本では解説の少ない「掘り出し物」について学べる
・ 大事なポイントを要約したので、時短
Contents
要約

第12章 掘り出し物を見つける
最良の機会は、たいてい周りのほとんどの人が気づいていないものの中からみつかる。
賢明なるポートフォリオの構築について
賢明なるポートフォリオ構築のプロセスは、
・ 特に収益性が高い資産を買い、
・ それらを買う余地を作るために収益性の劣るものを売り、
・ 最も収益性の低い資産は避けること
からなる。
このプロセスを実現するために必要な材料は、
① 投資先候補のリスト
② それらの本質的価値の推定
③ それらの価格が本質的価値と比べてどうなのかという感覚
④ それぞれの投資にともなうリスクと、
それらを組み入れることによるポートフォリオへの影響の理解
である。
あらゆる資産が投資対象になるわけではない

ポートフォリオ構築の第一歩は、投資対象がある種の絶対的基準を満たしているかどうか確認することだ。
しかし、あらゆる資産が投資対象になるわけではない。
リスクが許容範囲内にある投資対象に、候補を絞ることから始める投資家もいるだろう。
投資家によって、受け入れにくいリスクが存在するからだ。
例えば、どんな他のリスクは背負うが、
・ 動きの早いハイテク分野のリスクは避けたい者
・ 業界全体が不透明であるリスクを避けたい者
・ 企業の財務内容に不透明さがあるリスクを避けたい者
さまざまだ。
投資家(顧客)がとってほしくないと考えるリスクもありうる。
資産運用では、運用マネージャーに対して顧客は、特定のアセットクラスや投資スタイルを指定した上で運用を依頼する。
たとえば、大型優良割安株に投資した顧客は、それ以外の投資はしてほしくない。
マネージャーは、 他にどんな有望な投資先があっても、 顧客の要望に応えなければならない。
もし大型優良割安株投資でお金を集めて、ハイテク新興企業に勝手に投資をすれば、運用マネージャーのクビが飛ぶ。
したがって、ポートフォリオ構築の第一歩は、「あらゆる資産が対象になるわけではない」こと。
現実的な組み入れ候補となるものもあれば、候補から除外されるものもあるのだ。
投資は、相対選択の学問だ

「実行可能なリスト」が固まったら、次にその中から実際に投資する対象を選び出す。
具体的には、以下のようなものである。
・ リスクに対する潜在リターンが高いもの
・ 特に割安感が強いもの
35年経った今でも、私の心に残り続けている言葉がある。
投資は、相対選択の学問だ
シドニー・コイル
この簡単なフレーズには、2つの重要なメッセージが込められている。
1. 投資プロセスは厳格で規律正しくなければならない
2. 投資プロセスは必然的に相対的なものになる
価格が高騰や下落する、市場そのものを投資家は、変えることができない。
実在する投資候補の中から、「リターンは高いか」や「割安か」など考える。
いくつかの選択肢の中から、最良のものを選ぶしかない。
つまり、相対比較によって投資判断を下すのだ。
掘り出し物が生まれるプロセスとは?

理想的な投資をするための条件とは、主に「価格」にかかわることだ。
何を買うかではなく、いくらで買うかが問題となる。
質の高い資産は、掘り出し物にもつまらない物にもなりうる。
たいていの投資家は、優良資産とお買い得品の区別をつけることができない。
お買い得品とは、
・ 価格が、本質的価値と相対比較で見て低いこと
(価格<本質的価値)
・ 予想リターンが、リスクとの相対比較で見て高いこと
(リターン>リスク)
では、掘り出し物はどのようにして生まれるのだろう。
ヒントは、資産のバブル化の過程にある。
素晴らしい投資案件が、評判を得てしだいに過大評価のバブルへと変わる例は多い。
1. 素晴らしい資産を手に入れたいという人々の気持ちが高まり、
2. 資金がそこに流れ込み価格が上がる。
3. 価格上昇は、その資産が優れている証拠と 人々は受け止め、さらに買い増す。
4. それまで知らなかった者も、評判を聞いてその輪に加わり、
5. はてしない上昇トレンドとなる。
掘り出し物が生まれるプロセスは、おおむねその逆である。
つまり、掘り出し物を見つけるには、資産がどのように人気を失っていくかを理解することが不可欠だ。
人気低下は、分析することが難しいプロセスによるものだ。
そのため、
・ その背景に働く心理的な力と、
・ それを突き動かす評判の変化
について考えることが重要である。
掘り出し物は 、
・ きわめて不人気の資産である傾向が強い。
・ もともと客観的に見て何らかの欠点がある
・ 不人気ゆえに存在を無視されたり、毛嫌いされている
また、
・ 掘り出し物が生まれる背景には、いつも非合理性や理解不足がある
・ 掘り出し物の価格は、低空飛行。安いのは、懸念材料があるからとみなされる
高いリターンをもたらす株式は、もてはやされる。
一方で、リターンの低い債券は、ないがしろにされることが多い。
そんな中でも、債券がすばらしいパフォーマンスを上げる資産に生まれ変わるときがある。
きっかけは、投資家が「上昇余地」よりも「安全性」に対する選好を強めるような環境の変化である。
ある資産の価格がしばらくの間、上昇。
すると、ある日突然、投資家は今度は安全性の高い資産(債券)をあまり持っていないことに気づく。
その瞬間、「上昇余地」から「安全性」に気持ちが変わる。
不人気の資産がやがて大化けし、すぐれた投資先になる例

割安な資産を見つけ出すには、どこを探せばいいのか?
手始めに以下のようなものに目をつけるとよい。
・ あまり知られておらず、十分に理解されていない
・ ファンダメンタルズ面で疑問点がある
・ 議論のまとや恐れられている
・ ポートフォリオに組み入れるには、不適当とみなされている
・ 正しく評価されず、人気がない。
・ リターンが低迷しつづけている
・ 買い増しよりも、削減の対象となっている
ひとことでまとめると、次のようになる。
掘り出し物は、人々が実態よりも著しく悪い印象を抱いている状況でなければ見つからない。
最良の機会は、
・ 周りの人が気づいていないものの中から見つかる
・ 誰もがよいと感じ、喜んで買おうとするものにはない
あまり知られておらず、理解も尊重もされなかった資産が大化けした経験が、私にはある。
一時期、私は以下の運用を任された。
・ 転換社債
・ ハイイルード債
転換社債
株式と債券の二つの特徴をあわせ持つ商品。
社債で発行、途中で株式に変えることもそのまま債券としておくこともできる。
ハイイルード債
債務不履行の可能性のある債券。「ジャンク債」
「投資適格」の債券よりリスクが高い
これらの資産についてよいことを言う人は、当時皆無だった。
よく耳にしたのは、以下の意見。
・ 転換社債は、商品内容が複雑すぎる
・ 転換社債を買うなら、株と債券別々に買えばよい
・ 企業が気に入ったのなら、株を買えばよい
・ 債務不履行の危険のあるジャンク債を、年金運用者がもつのはありえない
・ 危険があることを十分に知りながら、ジャンク債に投資すればクビが飛ぶ
当時の私の保有する投資先は、まさにこの言葉そのものだった。
「居心地の悪さを覚える、型破りで無分別に思える投資先」
デイビット・スウェセン
しかし、不人気の資産がやがて大化けし、すぐれた投資先としての地位に上がった。
私が経験した2つの事例から、掘り出し物のありかを知るためのヒントになればと思う。
二次的思考をする者は、掘り出し物を手にすることができる

掘り出し物は 、 投資家にとって『聖杯』である。
なぜなら、掘り出し物は不当なまでに価格が低く、したがってリスクに対するリターンの比率が異常に高いからだ。
掘り出し物は、効率的市場に存在するはずがない。
ただし、私のこれまでの経験をもとに言えば、掘り出し物は、日常的には存在しないが、ごくまれに存在する。
「絶対お買い得品」とうたわれるものの多くは、あるはずがないうまい話である。
それらを避けることが投資で成功するための必須条件となる。
投資家は過ちを犯してしまう可能性がある。
・ 心理的弱さ
・ 分析上の誤り
・ 不安定な足場に立つことへの抵抗感
他の投資家が犯す誤りに気づくことができる 二次的思考者に、掘り出し物は提供される。
実践していること
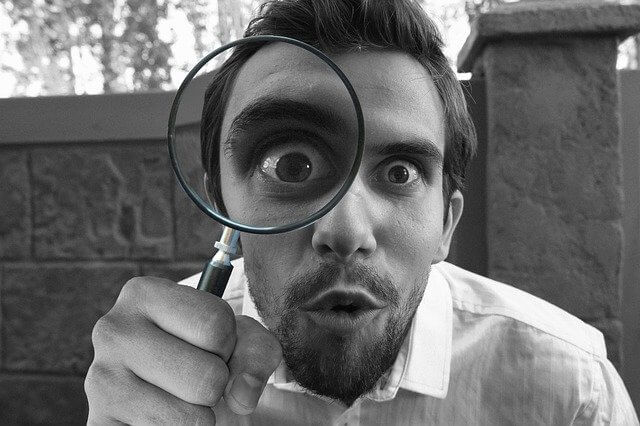

私は、
✔ 株式投資歴10年
✔ 本書愛読者
「投資で大切な20の教え 第12章掘り出し物を見つける」を学んで実践していることを紹介します。
ご参考までに。
「掘り出し物」だけにこだわらない

掘り出し物投資は、実際に実行してみると、とても難しいものです。
10年株式投資をしていますが、掘り出し物に出会うことは本当にまれです。
結論としては、「他の投資を実行しながら、掘り出し物も頭の片隅に入れて行う」です。
理由は以下の2点。
【理由1】掘り出し物を見つけることが難しい
【理由2】市場のきまぐれに付き合う必要がある
【理由1】掘り出し物を見つけることが難しい
掘り出し物は、
・ きわめて不人気の資産である傾向が強い
・ もともと客観的に見て何らかの欠点がある
・ 不人気ゆえに存在を無視されたり、毛嫌いされている
目に見える部分では、優良な投資先には見えてきません。
他の投資家が犯す誤りに気づくことができる二次的思考者に、掘り出し物は提供される
他人が気づかない目に見えない部分で、いかに企業を見極めることができるか。
「財務状況がいい」「高配当」など数字をみれば誰でも分かるものでは、判断できないということ。
引用文の「他の投資家」とは、百戦錬磨のプロの投資家も含みます。
多くの人や百戦錬磨のプロ投資家が、見抜けないところを自分だけ見抜き、投資で勝つ。
そう簡単ではないです。
【理由2】市場のきまぐれに付き合う必要がある
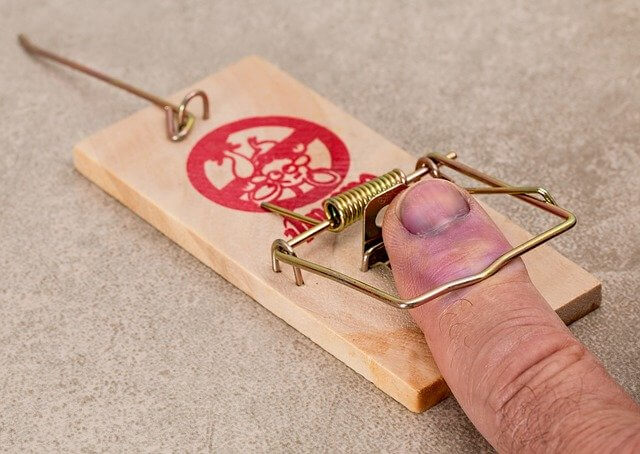
掘り出し物を見つける優れた目利きができるだけでは、勝利の女神は微笑んでくれません。
市場というきわめて不合理な世界が相手だからです。
掘り出し物は、効率的市場に存在するはずがない。
ただし、私のこれまでの経験をもとに言えば、掘り出し物は、日常的には存在しないが、ごくまれに存在する。
「銘柄選択は時間の無駄」と言えるくらい、市場は効率的。
ごくまれに、掘り出し物が見つかる程度。
市場は、あなたが支払い能力を保てる期間よりも長く、不合理な状態を続けることができる
ジョン・メナード・ケインズ(経済学者)
市場の方は、「間違ったまま」でも何年でもそのままでいることができます。
投資家の都合など、「知ったことではない」と言わんばかり。
過度の期待はしない
以上2点より、掘り出し物投資だけにこだわないことが大切です。
他の投資を実行しながら、頭の片隅に入れておく。
ただ、掘り出し物を探し続けることで、銘柄選択力が上がります。
掘り出し物投資の過程で、財務状況の数字など目に見えないものを考える必要があるからです。
投資の腕を上げるために、過度の期待をせず、「掘り出し物探し」をしてみてはいかがでしょうか?
まとめ

いかがでしょう。
まとめてみます。
第12章 掘り出し物を見つける
✔ 投資とは、 いくつかの選択肢の中から、最良のものを選ぶこと
(相対比較で投資判断を下す)
掘り出し物
・ きわめて不人気の資産である傾向が強い
・ もともと客観的に見て何らかの欠点がある
・ 不人気ゆえに存在を無視されたり、毛嫌いされている
✔ 掘り出し物を見つけるには、資産がどのように人気を失っていくかを理解することが不可欠。
✔ 割安な資産を見つけ出すには、以下を参考にする。
・ あまり知られておらず、十分に理解されていない
・ ファンダメンタルズ面で疑問点がある
・ 議論のまとや恐れられている
・ ポートフォリオに組み入れるには、不適当とみなされている
・ 正しく評価されず、人気がない。
・ リターンが低迷しつづけている
・ 買い増しよりも、削減の対象となっている
✔ 掘り出し物は、日常的には存在しないが、ごくまれに存在する。
✔ 他の投資家が犯す誤りに気づくことができる 二次的思考者に、掘り出し物は提供される。
