
「投資で一番大切な20の教え」って有名な本。
サクッと読める要約ないかな?
この記事は、「投資で一番大切な20の教え」という本の要約記事となります。
この記事でわかること
「投資で一番大切な20の教え」 第3章の要約から
・ マークスが考える、「バリュー投資」とは?
・ バリュー投資を行う上で大事にすること
・ マークスが説く、なぜバリュー投資が難しいのか?
この記事の信頼性
「投資で一番大切な20の教え」 著者は ハワード・マークス

ウォーレン・バフェットも一目置く投資家として有名。
バフェットいわく、「ハワード・マークスからの顧客向けレターは、真っ先に読む」とのことです。
オークツリー・キャピタル・マネジメントの会長兼共同創業者
オークツリー・キャピタル・マネジメントは、ロサンゼルスを拠点とした投資会社で、運用資産は8000億ドル以上。
高利債投資や不良債権への投資を得意とする。
ウォートン・スクールにて金融を学び、シカゴ大学にてMBAを取得。
引用 アマゾン 商品紹介ページ 「投資で一番大切な20の教え」より
この記事を書いた人

✔ 株式投資歴10年
✔ 国内外個別株、インデックス投資
✔ 投資関連本は山ほど読んで勉強しています!
投資で勝つには、著名投資家の本で学ぶことが一番の早道です。
そこでこの記事では、「投資で一番大切な20の教え」を要約しました。
・ バフェットがこの本を大絶賛。
大量購入してバークシャーの株主総会で配布したから
・ 世間でも「名著」と名高いから
・ 私自身も読んでみて、稀に見る有益な投資本だと考えるから
※ ご参考までに、アマゾンでの評価は★4つ(387件)

「投資で一番大切な20の教え」を繰り返し読んでいる者としては、

詳しく要約したほうが、読者に有益なのでは?
と感じました。
なぜなら、本文を読んでみると、投資家にとって、極めて有益な言葉が頻繁に出てくるからです。
ハワードの言葉や表現を大事にしながら、要約しました。
私にとって、本書は「投資のバイブル」です。
腹に落とし込むために、繰り返し読んできました。
しかし、こんな悩みもありました。

すごくいい本だけど、その都度最初から読むことは時間がかかるなぁ・・・
かといって、ネットの要約記事を読むと端折りすぎて物足りないし・・・


ハワードの言葉や表現を大切にした要約したもので、ササっと復習したいなぁ
同じような悩みのある方のお役に立てれば幸いです。
本記事をご覧いただければ、こんなメリットがあります。
・ マークス流のバリュー投資を理解できる
・ バリュー投資の難しさを再確認できる
・ 要約なので、時短
投資で一番大切な20の教え 要約
3 バリュー投資を行う 要約

投資で確実に成功するためには、まず最初に本質的価値を正確に推計することが不可欠だ。
本質的価値を下回る価格で買い、上回る価格で売れ
最も古くからある投資の原則は、最もシンプルである。
「安く買って、高く売れ」
「高い」「安い」には、何らかの基準が必要であり、その基準は「その資産の本質的価値」である。
「安く買って、高く売れ」 を言い換えると、
「本質的価値を下回る価格で買い、上回る価格で売れ」だ。
私にとっては、本質的価値を正確に推計することが、投資の出発点として欠かせないプロセスである。
株式投資する際のアプローチは大きく2つ。
・ 事業内容などに基礎的要因の分析に基づくアプローチ(ファンダメンタルズ)
・ 株そのものの値動きの研究に基づくアプローチ
ここでは、まず後者(値動きのアプローチ)について説明しよう。
なぜなら、値動きのアプローチは、その有効性を私が認めていないからだ。
・ テクニカル分析
・ モメンタム投資
・ テクニカル分析
一般に「テクニカル分析」と呼ばれるこの手法は、私がこの業界に入ったころから行われている。
しかし、テクニカル分析は、「ランダム・ウォーク仮説」の登場で著しく衰退している。
ランダム・ウォーク仮説とは、過去の株価変動が将来の株価変動の予測に全く役に立たないという仮説だ。
ある株式が10日連続で株価が上昇していたとしても、明日はどう動くかはわからない、と説く。
・ モメンタム投資
過去の株価動向を分析するアプローチに「モメンタム投資」もある。
モメンタム投資とは?
株価が上がっている時に買い、下がっている時に売る。
いわゆる「順張り投資」のこと。
上昇トレンドに波乗りするイメージ。
「モメンタム投資」も、私としては評価しがたい。
「モメンタム投資」は、上げ相場では有効かもしれないが、下げ相場では有効とは思えないからだ。
「永続できないものは、いずれ終わる」
の言葉のように、市場は上げ相場ばかりではない。
モメンタム投資が知性に訴える投資アプローチではないことは明らかだ。
例えば、デイトレーダーと呼ばれる人々。
彼らは、ポジションを翌日に持ち越すことはない。
1日の中で、何度も売買を繰り返す。
値上がり、値下がりの賭けを繰り返す行為を行う。
ある株式が10ドルから30ドル値上がりするとしよう。
デイトレーダーの場合、1ドルずつ儲けて合計3ドルの儲けとなる。
| デイトレーダー | 買値 | 売値 | 儲け |
| 第1週(の1日) | 10 | 11 | 1 |
| 第2週(の1日) | 24 | 25 | 1 |
| 第3週(の1日) | 39 | 40 | 1 |
普通の株式投資の場合、第1週に買い、第3週まで保有し売却するから30ドルの儲けとなる。
| 普通の株式投資 | 買値 | 売値 | 儲け |
| 第1週~第3週 | 10 | 40 | 30 |
30ドル値上がりした株式で3ドルの儲けしか出ないデイトレード。
デイトレードで儲けようとする人のことが、私にはまったく理解できない。

「テクニカル」「モメンタム」ともに経験あります。
結果から言うと散々でした・・・
投資というより「トレーディング」ですから、難しいんですよね。
「バリュー投資」「グロース投資」は、どちらも将来性を考慮する必要性がある

・ 事業内容などに基礎的要因の分析に基づくアプローチ(ファンダメンタルズ)
・ 株そのものの値動きの研究に基づくアプローチ
のうち、前者(ファンダメンタルズ)に話を進めよう。
ファンダメンタルズには、大きく2つのアプローチがある。
「バリュー投資」
「グロース投資」
である。
簡単に言えば
| バリュー投資 | 証券の現在の本質的価値を推計し、価格がこれを下回った時に買う (本質的価値 > 価格) |
| グロース投資 | 将来、本質的価値が急増する証券を見つけ出そうとする投資方法 |
企業の価値を決めるものは何か?
金融資産、経営力、工場、小売店舗、特許、人的資源、ブランド力、潜在成長性、そして何より利益とキャッシュフローを生み出す力だ。
バリュー投資では、実物資産やキャッシュフローといった目に見える要素を重視する。
長期的な成長性といった実体のない要素には、あまり重点を置かない。
バリュー投資で追及するのは安さである。
財務指標に注目し、安いと判断したら判断した銘柄を買うことを重視する。
グロース投資は、将来有望な企業をつきとめることを重視する。
つまり、企業の現在の業績などにあまり重きを置かず、将来性をより重視する。
2つの主要投資アプローチの違いを要約してみよう。
| バリュー投資家 | 現在の本質的価値が、現在の株価との相対比較で見て高いと判断すれば買う (現在の本質的価値 > 現在の株価) |
| グロース投資家 | (株価が高くても)将来的に、十分な利益を生み出すほど本質的価値が急増すると確信すれば買う |
私は、「バリュー投資」「グロース投資」両者の違いを
・ 「バリュー投資=割安感」、「グロース投資=成長性」 ではなく
・ 「今日の本質的価値」と「明日の本質的価値」のどちらかを重視すること
ではないかと考える。
バリュー投資とグロース投資をはっきり線引きすることはできない。
「バリュー投資」「グロース投資」、どちらの場合でも将来性を考慮する必要性があるからだ。
バリュー投資家は、割安だけでなく、企業の(将来の)成長性も勘案する。
グロース投資家は、(将来の)成長性があって、割安な銘柄に投資する。
要するに、何にどれだけの重きを置くかという程度の問題である。
・ グロース投資は、将来性を重視
・ バリュー投資は、現在の本質的価値を重視
・ さらに、バリュー投資は、将来性も織り込まないわけにはいかない
とまとめるのが妥当だ。
バリュー投資を選ぶ理由

将来性に重きをおく、グロース投資の極端な例。
「ニフティ・ニフティ(すばらしい50銘柄)」の話をしよう。
1968年、私は投資業界で働き始めた。
そのころ、「ニフティ・ニフティ投資」が行われていた。
ニフティ・ニフティ投資とは、
・ 高い成長性
・ 十分な質(高い成長性が実現する可能性が高い)
・ 兼ね備えた銘柄なら、価格はどうでもかまわない(高くても買う)
という手法
仮に高値で買うことになっても、数年たてばその株価に見合った企業に成長する、という考え方だ。
当時、これに該当する銘柄を一部挙げると、以下の企業たちである。
・ IBM
・ ゼロックス
・ コダック
・ ポラロイド
・ メルク
これらかつての米国の優良企業は、40年経ってどうなっただろうか?
多くの企業が衰退したり、倒産したりしてしまった。
結論はこうだ。
企業の長期的な成長性とそれを正確に予測する能力には限界があるのだ。
一般的に、グロース投資は、将来予測に伴う不確実性があるため、大勝ち狙いが中心となる。
また、成功率も低くなる。
最良の新薬、最強のコンピューター、大ヒット映画をどの企業が生み出すかを正確に予測することが難しいからだ。
その代わり、グロース投資は、成功した場合リターンが劇的に増大する可能性がある。
一方で、バリュー投資で成功した場合でもリターンはより安定的である。
私自身は、バリュー投資を選ぶ。
ドラマチックさより安定性を重視するからだ。
バリュー投資が難しい理由

安定的に好ましい結果が得られる可能性があるというのなら、バリュー投資は簡単だろうか?
答えはノーである。
理由は2つある。
1. 本質的価値を正確に推計することが難しいこと
2. ブレずにいることがむずかしいこと
1. 本質的価値を正確に推計することが難しいこと
正確に推計できなければ、高すぎる価格や安すぎる価格でその銘柄を買うことになる。
問題は、高すぎる価格で買うことである。
・ 予想外の本質的価値の増大、
・ 強気相場、
・ もっと見る目のない投資家が買う(「より愚か者」といわれる)
でもないと利益は上がらない。
2. ブレずにいることがむずかしいこと
投資の世界では、何かが正しかったとしても、必ずしもすぐに証明されるわけではない。
本質的価値に関する見方を我慢強く保持することが、利益の獲得につながる。
たとえば、本質的価値80と見積もった企業の株を、60で買ったとする。
この場合、自分の判断は正しかったと感じるだろう。
しかし、株価60で買った株が、さらに下がって株価50になればどうなるか?
買い時の判断を誤ったのではないか?と疑いはじめ、不安になる。
このため、
・ 資産を保有し続けること
・ ナンピン買いをすること
は、非常に難しくなるのだ。
さらに状況は悪くなる。

もしかしたら、自分の判断はまちがっていて、市場のほうが正しいのではないか?
下げ止まらない!ゼロになる前に株を手放した方がいい!

このような投資家心理が、売りを加速させるのだ。
・ 利益や配当
・ 株価水準
・ 事業内容
について無知(あるいは無関心)な投資家は、単純に正しいことを正しいタイミングで行うのに必要な強い意志を持つことができない。
株価水準について正しい見解を持っていても、意志が固くないとあまり役には立たない。
誤った見解を持った人が意思が固い場合、状況はさらに悪くなる。
すべてを正しく行うことは、とても難しい。
ファンダメンタルズ分析に基づいて導き出された本質的価値が最もふさわしい
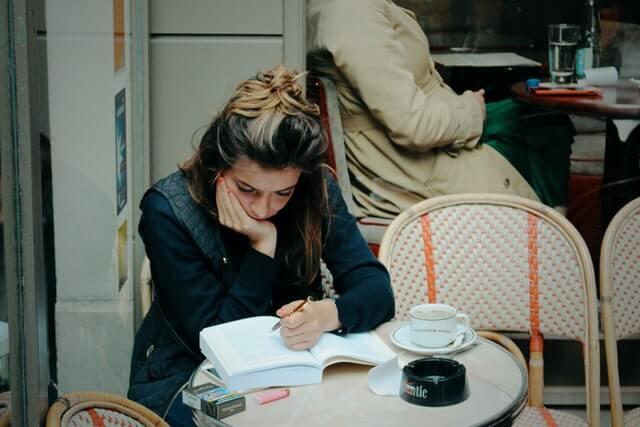
多くの投資家は、「値上がりする銘柄」を探している。
しかし私の考えは、投資のよりどころにするのは価格ではない。
ファンダメンタルズ分析に基づいて導き出された本質的価値が最もふさわしい。
本質的価値を正確に推計することは、
・ 感情に流されない着実な投資
・ 利益を生み出す可能性の高い投資
に不可欠な土台である。
投資家が下げ相場でも利益を上げるためには、不可欠な条件は3つある。
・ 本質的価値に関する見解を持っていること
・ その見解を我慢強く持ち続けること
(値下がりして、自分が間違っているという気になっても買う)
・ その見解が正しくなければならないこと
学んで実践していること

「投資で一番たいせつな20の教え」第3章を読んで、実際に行動していることをご紹介します。

読んでどんなことすればいいんだろう?
とお考えでしたらご参考までに。
実践していること
・ 本質的価値を常に考える
本質的価値を常に考える

結論としては、
「企業の本質的価値は測定が非常に難しい。でも、考え続ける」
です。
第3章には、大きな問題があります。
「企業の本質的価値をいったいどう求めたらいいかを書いていないこと」 です。
一方で、企業の本質的価値を正確に測定することは非常に困難です。
困難にしている理由はさまざまです。
たとえば、
・ 企業が持つブランド力の資産価値の測定が難しいこと
・ 目に見えない資産価値の測定が難しいこと
ブランドでは、例えばアップルのiPhone。
アップルのイメージと言えば、
・ 洗練されている
・ 計算されつくしたシンプルさ
・ 利用者のことを徹底して考える
ライバルがまねできない圧倒的な差別化を実現し、利益の源泉になっているアップルのブランドイメージ。
長年にわたり、構築されたブランドイメージには、いったいどのくらいの資産価値があるか?
目に見えない資産では、例えば優秀な人材や経営者。
企業にとって人材は宝であり、利益の源泉になっているのは間違いありません。
計り知れない資産価値はありますが、いったいどのくらいの資産価値があるのか?
このように、企業には資産価値があるけど金額で示せないものもたくさんあるので、本質的価値を測るのは難しい。
一方で、引用では、このようにあります。
企業の価値を決めるものは何か?
金融資産、経営力、工場、小売店舗、特許、人的資源、ブランド力、潜在成長性、そして何より利益とキャッシュフローを生み出す力だ。
目に見えない、資産価値が分からないものでも、最後には利益とキャッシュフローという形で現れると考える事ができます。
では、利益とキャッシュフローだけを見ていれば、企業の本質的価値を知ることができるのでしょうか?
引用にもあるように、金融資産や経営力・・とあるようにさまざまなものを考える必要があります。
私は、投資家として、常に

企業の本質的価値とはなんだろう?
と考え続け、答えを探しています。
そうすることで、企業というものの理解が深まっていきました。
なぜなら、「企業の本質的価値とは?」という難問に答えがないからです。
答えがないから、自分の頭でいろいろ考えざるを得ないし、勉強せざるを得ない。
答えがないから、その探求に終わりはありません。
株式投資を続ければ、ずっとこの難問と付き合うことになりそうです。
株価だけを見る投資家になるのか?
「企業の本質的価値とは?」と常に考え続けて投資家になるのか?
投資の勝率が上がり、投資家として成長できるのは、第3章を読むとやはり後者。
結論は、
「企業の本質的価値は測定が非常に難しい。でも、考え続ける」
です。
まとめ

いかがでしょう?
まとめてみます。
投資で一番大切な20の教え 要約
3 バリュー投資を行う 要約
✔ 最も古くからある投資の原則は、「安く買って、高く売れ」
✔ 企業の長期的な成長性とそれを正確に予測する能力には限界がある
✔ 「バリュー投資」「グロース投資」、どちらの場合でも将来性を考慮する必要性がある
✔ 投資のよりどころにするのは価格ではなく、ファンダメンタルズ分析に基づいて導き出された本質的価値が最もふさわしい
✔ 投資家が下げ相場でも利益を上げるためには、不可欠な条件は3つ
・ 本質的価値に関する見解を持っていること
・ その見解を我慢強く持ち続けること
(値下がりして、自分が間違っているという気になっても買う)
・ その見解が正しくなければならないこと
学んで実践していること
実践していること
・ 本質的価値を常に考える
ご参考までにどうぞ
