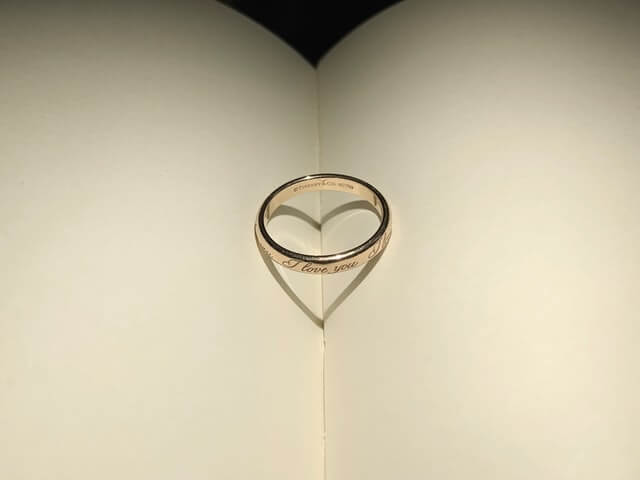「投資で一番大切な20の教え」って有名な本。
サクッと読める要約ないかな?
もう少し詳しい要約した記事ないかな?

このように、お考えではありませんか?
この記事でわかること
「投資で一番大切な20の教え」の8章要約から
・ 「浮き沈み」と表現されるサイクルが、投資に及ぼす影響と対処の仕方
・ なぜ、著名投資家マークスが「サイクルの存在」を重要視するのか
この記事の信頼性
「投資で一番大切な20の教え」という本の要約記事となります。
著者は ハワード・マークス

ウォーレン・バフェットも一目置く投資家として有名。
バフェットいわく、「ハワード・マークスからの顧客向けレターは、真っ先に読む」とのことです。
オークツリー・キャピタル・マネジメントの会長兼共同創業者
オークツリー・キャピタル・マネジメントは、ロサンゼルスを拠点とした投資会社で、運用資産は8000億ドル以上。
高利債投資や不良債権への投資を得意とする。
ウォートン・スクールにて金融を学び、シカゴ大学にてMBAを取得。
引用 アマゾン 商品紹介ページ 「投資で一番大切な20の教え」より
この記事を書いた人

✔ 株式投資歴10年
✔ 国内外個別株、インデックス投資
✔ 投資関連本は山ほど読んで勉強しています!
投資で勝つには、著名投資家の本で学ぶことが一番の早道です。
しかし、投資本がたくさんあり、有益なのか分かりづらいという問題があります。
そこで、「投資で一番大切な20の教え」を紹介します。
・ バフェットがこの本を大絶賛。
大量購入してバークシャーの株主総会で配布したから
・ 世間でも「名著」と名高いから
・ 私自身も読んでみて、稀に見る有益な投資本だと考えるから
※ ご参考までに、アマゾンでの評価は★4つ(387件)

本記事は、「投資で一番大切な20の教え」要約です。
いろいろな要約記事をネットで拝見しました。
「投資で一番大切な20の教え」は、投資中級者向けの本です
多くの要約記事では、難しいものを大変にわかりやすく説明されています。
「投資で一番大切な20の教え」を繰り返し読んでいる者としては、

もう少し詳しく要約したほうが、読者にもっと有益なのでは?
と感じました。
なぜなら、本文を読んでみると、投資家にとって、極めて有益な言葉が頻繁に出てくるからです。
そのような言葉のシャワーを、読者が浴びることを大事にしながら、要約しました。

最初、本屋で「はじめに」を立ち読み。
体にビビッときました、「これはすごい名著だ!」と。
本書を「投資のバイブル」として、繰り返し読んできました。

すごくいい本だけど、その都度最初から読むことは時間がかかるなぁ・・・
かといって、ネットの要約記事を読むと端折りすぎて物足りないし・・・

そんな悩みがありましたので、同じような悩みのある方のお役に立てれば幸いです。
本記事をご覧いただければ、こんなメリットがあります。
・ 投資に存在する「サークル」を学び、投資戦略に生かすことができること
・ 「サークル」の存在を認識し、投資の勝率を上げることができること
Contents
要約

第8章 サイクルに注意を向ける
ほとんどすべてのものにはサイクルがある、と肝に銘じることが必要不可欠である。
ひたすら一方向に動き続けるものはない。
そして、今日の出来事を未来に当てはめることへのこだわりほど、投資家の健康を脅かすものはない。
サイクルの極端な振れは、人の感情が原因

投資の期間が長くなるにつれ、私は物事につきまとうサイクルの存在をますます強く感じている。
原則① ほとんどの物事にはサイクルがあることがやがて判明する
原則② 利益や損失を生み出す大きな機会は、周りの者が原則①を忘れたときに生じることがある
物事には、上昇と下降、成長と衰退を繰り返すという基本原則だ。
経済、市場、企業も例外ではない。
必ず浮き沈みがあるのだ。
我々が生きている世界にサイクルが存在する根本的な原因は、人がかかわっていることにある。
歴史や経済学といった分野では、その過程に人がかかわっており、人がかかわれば、結果は変化と浮き沈みに富んだものとなる。
なぜなら、人は感情的で一貫性のない生き物だからだ。
サイクルの極端な振れは、もっぱら人の感情や欠点、そして客観性と一貫性が欠けていることに起因する。
世界中の出来事、企業の意思決定など、客観的な要因もサイクルにおいて大きな役割を果たす。
世界中の出来事、企業の意思決定など客観的要因に、人の感情的な心理要因が加わる。
すると、投資家は過剰、あるいは過小な反応を示し、これがサイクルの波の大きさを決定づけるのだ。
サイクルには、自律調整能力がある

信用サイクルは、不可避で、振れが極端に激しく、順応力のある投資家にチャンスをもたらすという点で特筆に値する。
「信用サイクル」とは?
・ 「クレジットサイクル」とも呼ばれる
・ デフォルト(債務不履行)の上昇が一定の周期で発生するという現象
・ 企業や家計などの借入状況(信用面)の浮き沈みが循環することを示すもの
・ 一般的には、拡大・後退・修復・回復の4つの局面を繰り返すとされます
引用 iFinance 「クレジットサイクル」 より ~箇条書きに一部加工~
信用規模の拡大のプロセス
1. 経済が好況になる
2. お金を貸し出す金融機関が儲かり、お金がたまる
3. 好況で悪い材料がなく、投資や融資のリスクが低下したように見える
4. 人々の「リスク回避思考」が消える
5. 金融機関が事業拡大、資金提供の拡大に動く
6. 金融機関が、他の金融機関と争うため、金利の引き下げや融資の基準を下げてお金を貸す
信用規模の拡大期には、本来なら融資に値しない借り手やプロジェクトに、金融機関は資金を供給するようになる。
「最悪の融資は景気が最もよい時期に行われる」
そして、資金が全く回収できなくなる事態が起きはじめる。
信用規模の縮小のプロセス
1. 損失を出した金融機関が、融資姿勢を消極化させる
2. リスク回避思考が強くなり、金利の引き上げや融資基準の厳格化が始まる
3. 金融機関が貸し出すお金も減り、超優良な借り手しか相手にしなくなる
4. 企業が資金不足になり、倒産する
5. こうしたプロセスが、景気後退を招き、さらに拍車をかける
信用規模の縮小のプロセスが行き過ぎると、サイクルは再び反転(信用規模拡大)に向かう。
サイクルには、自動で反転する、自律調整力がある。
信用サイクルは、信用規模の拡大、縮小の2つのプロセスを通じて自動的に反転するのだ。
サイクルは決してなくなることはない

サイクルの波がなくなることは決してない。
市場に大きな影響を及ぼす「人々の感情」が存在するからだ。
消費者が様々な要因に対して、感情的に反応し、支出を増やしたり減らしたりする。
景気は、拡大と後退を繰り返す。
企業は、景気拡大期にはバラ色の未来を描き、設備在庫を増やす。
やがて、景気後退期になると、過剰な設備在庫が重くのしかかる。
銀行などの金融機関は、好況期には、融資姿勢を大幅に緩める。(低金利で融資)
景気が悪くなると、融資姿勢を急激に厳しくする。
投資家は好調時の企業を過大評価し、状況が悪化すると過小評価する。
10年に1度ぐらいの間隔で人々は「サイクルはなくなった」と思い込む。
トレンドは、一方向への流れが永遠に続くと主張する者が現れる。
しかし、「サイクルはなくなった」という思い込みは、「今回は違う」という危険な前提に基づく考え方の典型例だ。
サイクルの上昇局面でも下降局面でも、ほとんどの場合、未来は過去と非常によく似た状況になる。
そして、反転すると判断するのにふさわしいタイミングがある。
サイクルを無視し、これまでのトレンドをそのまま未来に当てはめようとすることは、投資家が冒しうる重大な危険のひとつである。
トレンドは、いつか反転するほうが、現実となる公算は大きい。
経験を積んだ投資家なら、サイクルがなくなることはありえないと気づき、その認識を自らの強みとするべきだ。
まとめ
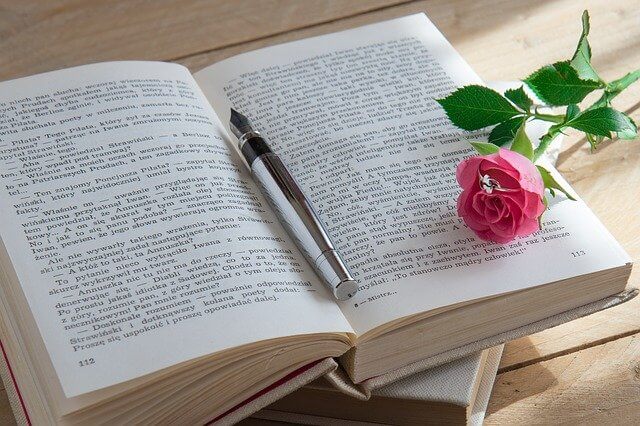
いかがでしょう?
まとめてみます。
✔ 投資では「浮き沈みする」サイクルが存在する。その原因は、人の感情にある
✔ 信用サイクルは、振れ幅が大きいが投資家にチャンスをもたらす
✔ サイクルには自律調整能力があり、行き過ぎれば自動で反転する
✔ サイクルの波がなくなることは決してない。
✔ 投資家は「サイクルはなくなることはない」を認識し、投資に臨むこと