
「バフェットの法則」って本、いまでも読むべきなのかな?
この記事では、ウォーレン・バフェットの投資術を解説した本、『バフェットの法則』を紹介します。
内容としては、おススメする5つの理由となります。

この記事を書いた人

- 株式投資歴10年。バフェット本読書歴9年。
- 大損してバフェット投資術に出会う
- バフェット投資術実践中
本格的にバフェット投資術を学ぶ上で、避けては通れない本です。
Contents
「株で富を築くバフェットの法則」おススメする5つの理由
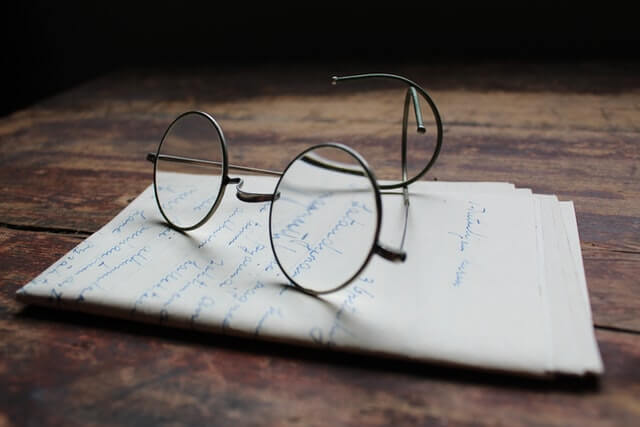
おススメする5つの理由
- 文章が分かりやすいこと
- バフェット投資術の全体像がつかみやすいこと
- バフェットが行った実際の企業買収の説明が分かりやすいこと
- バフェットファンならではの深い考察があること
- 2人の投資の巨人の文章が読めること
以下、詳しく解説していきます。
1. 文章が分かりやすいこと

筆者が、バフェット投資術の説明が、とても上手いこと。
それに加えて、日本語訳も分かりやすい。
投資本でよくありますが、「日本語訳が硬くて読みにくい」。
本書では、そのような小難しさがありません。
理由としては、
- 日本語訳が、女性が書いた翻訳のように柔らかい日本語であること
- 翻訳者 小野一郎さんが投資の理解が深いから
読んでみてもスラスラ読めますし、読み返しも少ない。
2. バフェット投資術の全体像がつかみやすいこと

バフェット流投資術を、様々な角度から説明している。
生い立ち、投資の先生。
投資術、株式の管理から心理学と幅広い。

これだけの大ボリュームをよく一冊でまとめたなぁ・・
私は、数多くのバフェット関連本を読んできました。
しかし、ここまでいろいろな角度からバフェットに切り込んでいる本はないです。
多面的だからといっても、それぞれが広く浅くではなく、内容も濃い。
「バフェット投資術を本格的に学びたい」と願う投資家には、避けて通れない本です。
ベストセラーであり、著名投資家が紹介文を寄せたのも、納得がいく出来です。
3. バフェットが行った、実際の企業買収の説明が分かりやすいこと

4章は、実際にバフェットが行った企業買収の9つのケースを詳しく解説しています。
3章で上げた12原則を用いながらの企業買収の解説は本当に分かりやすい。
なぜなら、バフェットの買収事例は、普通に眺めていても難しいからです。
他の本でも、バフェットの買収にふれているものもありますが、
- バフェットがなぜこの会社に目をつけたか分からない
- どういうことを考えての買収なのかよく分からない
しかし、本書では、3章で12の原則を挙げて説明したうえで、4章で実際のバフェットの株式投資の実例を解説。
個々の投資事例に対して、原則を当てはめて説明しているので、分かりやすい。
先に挙げた疑問、
- なぜ、バフェットはこの会社を選んだのか?
- どういう考えで、バフェットは投資に臨んだのか?
がはっきりしてきます。
4. バフェットファンならではの深い考察があること
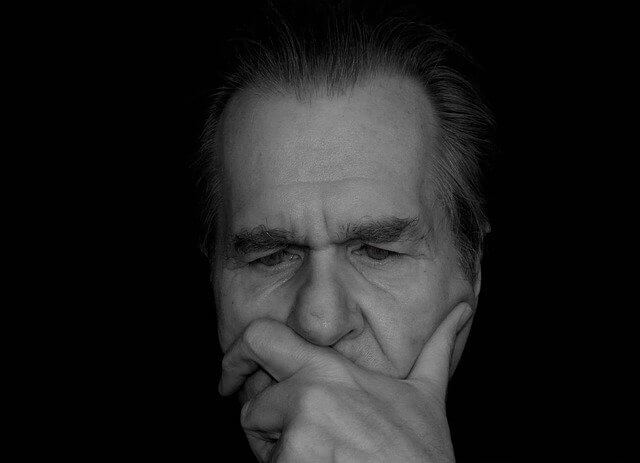
バフェット投資術では難しいところもありますが、本書では見事に説明しています。
読んでいても、難しい箇所をサラッと上手に説明してありますので、驚きます。
1.筆者は、長年のバフェット研究でバフェットのことがよくわかっていること
2.多くのバフェット関係の書類を読んでいるので、バフェット投資術の全体像を筆者がしっかり理解していること
「難しい」ものを誰でも「分かりやすく」説明するためにはどうしたらいいでしょうか?
より深く理解することです。
誰よりも深く「理解」することで、「要はこういうこと!」とポンと説明ができます。
本書では、そういった記述が多く見られます。
バフェットの考えや投資術を個々の「点」とすると、うまくつなぎ合わせて「線」にして説明している。
長年の研究により導かれた、バフェット投資の本質に迫るようです。
5. 2人の投資の巨人の文章が読めること

偉大な投資家2人から見た「バフェット」に関する文章は貴重です。
共に「抜群な投資実績」「有名な投資本の著者」という共通点があります。
ハーワード・マークスは、「投資で一番大切な20の教え」という名著と名高い投資本の著者。
ピーター・リンチは、「ピーター・リンチの株で勝つ」という名著として名高い投資本の著者。
投資をしている人にとって、知らない人はいない有名人の文章が読める。
バフェットが一目置く投資家2人。ここだけでも読む価値があります。
悪い点

1点だけ気になる点を。
悪い点
- データが古いこと
1. データが古いこと
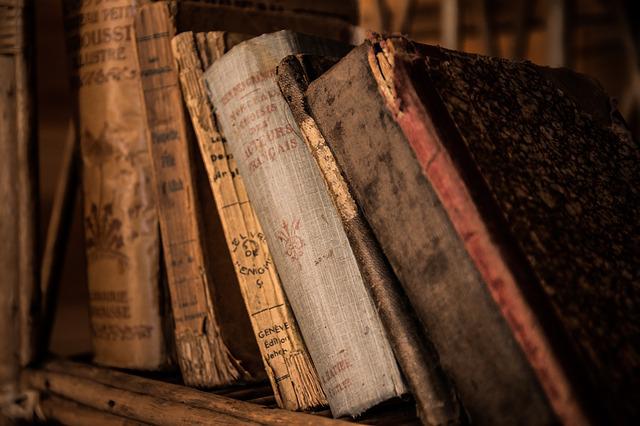
「バフェットの法則」は2014年発売と、今となっては少し古い本です。
当然ながら、掲載しているデータも古い。
しかし、本書のデータ自体は多少古くても、何ら問題ありません。
なぜなら、バフェット投資術の基本となる考え方、原理原則は、長年大きく変わっていないからです。
たとえば、バフェットの「安全マージン」という考え方。
簡単に言えば、「株を安く買う」考え方のこと。
この「安全マージン」を投資の軸にしている点は、バフェットの若いころから今に至るまで変わりません。
ただ、バフェット投資術は、進化している部分もあります。
2014年発売の「バフェットの法則」が、2022年現在のバフェットの一言一句、全く同じかといえば、少し違います。
たとえば、かつてはハイテク嫌いで有名だったバフェット。
いまでは、iPhoneでおなじみの「アップル社」の株を大量に保有している変貌ぶり。
バフェット投資術を学ぶ上で、極めて有効な本であることには、今も変わりません。
なぜなら、バフェットの投資の軸自体は、長年変わっていません。
そして、さまざまな面からバフェットを観察し、深く考察しているバフェット本はほかにないからです。
以上、「2014年発売でデータは古い。だけど、バフェットの法則は今も学ぶべき本である」という結論です。
まとめ:バフェット投資術を、いろいろな角度から分析した投資本の名著

この記事では、「株で富を築く バフェットの法則」という本をおススメする5つの理由を述べました。
2014年発売と、本自体、多少古くはなりました。
しかし、バフェットの投資術は、長年大きく思考の軸が変わっていません。
今でも、投資家が、読むべき投資本の名著には変わりません。
ぜひ、一度手に取っていただき、多くの投資家の方に読んでいただきたい、おススメの本です。
