
投資に必要な忍耐力を身に着けたい!
どうしたらいいのかなぁ?
この記事では、ウォーレン・バフェットの投資術を解説した本、『バフェットの法則』を紹介します。
内容としては、「第7章 投資に必要な忍耐力」を要約した記事となります。

投資で成功するためには、忍耐強く長期的に考えることが最高であることは、多くの証拠が示すところである。
引用 『バフェットの法則』 第7章 投資に必要な忍耐力 より
ウォール街は動くことで金が転がり込んでくる。
あなたは動かないことで金が転がり込んでくる
出典 『バフェットの教訓』 メアリー・バフェット/デビッド・クラーク 著 出版 徳間書店
ウォーレン・バフェット
この記事で分かること
- バフェットにみる、投資での「忍耐力」の使い方
- 投資における忍耐力の重要性(客観的な研究結果)
- 【学びを実践】投資における「忍耐力」をつけるためにしていること
この記事の信頼性
- 「バフェットの法則」という本を丁寧に要約
- 筆者 ロバート・G・ハグストロームさんは、長年のバフェット研究家
- ロバートさん自身、バフェット投資術を使ったファンドを運用
筆者の言葉を、大切に丁寧な要約を心がけました。
この記事を書いた人

- 株式投資歴10年。バフェット本読書歴9年。
- 大損してバフェット投資術に出会う
- バフェット投資術実践中
この記事を読むメリット
- バフェットの「忍耐力」の使い方が分かる
- 投資における忍耐、知っておいた方がいいことがわかる
- 【時短】要約なので、短時間で学べる
「バフェットの法則」は、バフェット投資術を全体像をとらえ、比較的やさしく解説している本です。
残念ながら、具体的な株の銘柄選定の仕方や、いくらで買うかなどの記載はありません。
しかし、
- 投資の心構えや知っておきたいこと
- 自分でひとりで投資する際、軸となる投資の考え方
が満載です。
本記事をご覧いただき、強靭な「忍耐力」を身に着けることで、投資成績の向上が見込めます。
Contents
投資に必要な忍耐力 7章要約
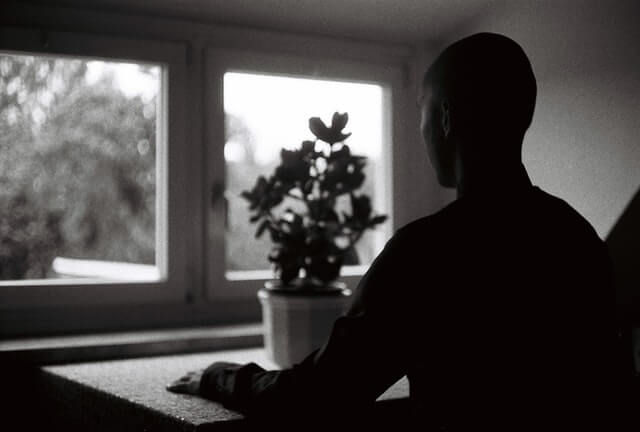
一般的に、
- 短い時間軸で行われる活動は、『投機』
- 長い時間軸で行われる活動は、『投資』
と考えられる。
バフェットは、静かに長い時間投資する。
多くの人が、できるだけ早く、たくさん儲けようとするのはなぜか?
市場の心理は予測可能と勘違いしているのだろうか?
弱気相場や経済危機を経験して、長期投資に失望してしまったのだろうか?
すべての疑問の答えは、イエスである。
一番悩ましい問題は、
- 投資家が「長期投資へ失望」して、長期投資をやりたがらないこと
- バフェット流投資の根本は、「長期投資」であること
- 投資での成功は、長期投資がカギ。しかし投資家が長期投資に失望してしまって、やりたがらないこと
である。
1. 長期間が大事

2人の学者が、長期と短期の投資戦略を比較した研究を発表した。
アンドレイ・シュライファーとロバート・ヴィシュニーである。
比較したのは、「コスト」「リスク」「リターン」の3項目。
短期の場合、「コスト」「リスク」が低いため「リターン」が低くなる。
長期の場合、「コスト」「リスク」が大きくなるため、「リターン」が大きくなる。
※ ここでいう「コスト」は、投資していた期間と定義されています。お金ではありません。
| コスト | リスク | リターン | |
| 短期 | 低い | 低い | 低い |
| 長期 | 高い | 高い | 高い |
2人は、普通株式を使って短期的な取引ができると記している。
短期投資(投機)をする人のコストは短期間だから、ごくわずかだ。
結果が出るまでの不確実性というリスクも少ない。
しかし、リターンは小さくなる。
投機は短期で勝負し、小さな儲けで満足する。
投資は長期的に考え、大きなリターンを得る。
長期期間で投資を行うことは、本当に大きなリターンを得ることができるのか?
さまざまな調査の結果、長期投資を行うと大きなリターンを得られることに、議論の余地はなかった。
この調査結果には、「ただし」という条件が付く。
- 優れた銘柄選定の能力があること
- 優れたポートフォリオ管理ができること
以上は、そのままバフェット流の投資手法になる。
バフェット流投資原則を活用できる投資家は、銘柄の入れ替えを抑えて長期間投資をすれば、多くのリターンを得ることが可能である。
1950~1970年までにおいて、株式の平均保有期間は4~8年間だった。
1970年初頭から、保有期間はどんどん短くなってきた。
わたしたちの調査によれば、市場を大きく上回る差額を手に入れるチャンスは「3年間保有したあとに最大」になる。
つまり、少なくとも毎年すべての銘柄を入れ替えているポートフェリオでは、多くの投資家がこのチャンスを逃すことになる。
株式の保有期間の減少は、長期投資家の減少を意味する。
長期投資を行っていた人々が、短期の投機に移ってきたため、「長期投資」より「短期投機」を行う人が増えた。
その結果、以下のようになった。
- 短期での投機は、以前より勝つことが難しくなり、リターンも小さい
- 短期のトレーダーへの誘惑は強く、たくさんの投資家を引き込んでしまう
- 長期投資をする人が少なくなり、大きなリターンを得ることが可能となった
2. 『合理性』とは何か

合理主義とは、意見や行動が感情ではなく、理性と知識に基づいて行われるべきだという信念や考え方のこと
合理性は知性と同じではない。
キース・スタノビッチ大学教授は、以下のように話す
知能指数やSATなどのテストは、合理的な思考の測定にはほとんど役に立たない
さらに、スタノビッチはその著書の中で「理性障害」という用語を使って説明する。
『理性障害』とは、高い知性があっても、合理的に考えて、行動することができないこと
認知心理学では、理性障害の2つの主たる原因があるとする。
「情報処理の問題」「内容の問題」である。
※「内容の問題」は、 5.マインドウェア・ギャップ(後述)にて詳細に触れています
「情報処理の問題」は、そもそも人間は情報処理が苦手であること。
人間は、問題を解くときに計算を使うときがある。
しかし、計算には、時間がかかり集中を要する。
一方で、計算も行わず、集中も要さない「即決」する思考もある。
人間は思考に労力を使おうとしません。
不正確であっても、計算しないで済む方法を好むようにできているのです。
3. ゆっくり伝わる情報

情報の役割について考えてみよう。
ここで言う情報とは、この章のテーマである、忍耐に関係する、ゆっくり伝わる情報のことである。
ジャック・トレイナーは、ファイナンスの分野で重要な人物。
トレイナーは、長年にわたってファイナンス分野の研究者と論文を交換してきた。
その中には、ノーベル賞を受賞したフランコ・モディリアーニなどそうそうたる顔ぶれ。
トレイナーは著書の中で「市場の効率性」をテーマにした。
この問題に対して、トレイナーは「投資に関する2つの情報を区別すること」を提案している。
その区別とは、
- 直接的で、内容が明白な情報(短時間で広く伝わる)
- 評価するためによく考え、判断力と熟練が必要な情報(伝わり方もゆっくり)
トレイナーの結論は
「短時間で伝わる情報は、大多数の人が評価するので間違いがない」
短時間で伝わる情報として、PER、配当利回り、テクニカルチャートなど株式に関する初歩的な情報が挙げられる。
別の言い方をすれば、短時間で広く伝わる情報には、それだけでただちに利益をもたらしてくれない。(多くの人が間違えないから)
しかし、ゆっくり伝わる情報こそが、長期投資の有意な基礎となる。
バフェット流投資原則は、「ゆっくり伝わる」情報であり、長期のビジネスに発展するものである。
ゆっくり伝わる情報は、頭で理解することは難しいわけではない。
単純明快で明白な情報に頼るよりも労力を要する。
4. システム1とシステム2

人の認識は2つに分けられる。
「システム1」「システム2」と呼んでおり、特徴は以下の通りである。
| システム1 | 素早く連想させるもの(直感) |
| システム2 | ゆっくりした、ルールによって管理されたもの(熟考) |
システム1は、時間がかからず、細かい計算をするような知性を使わない。
システム2は、じっくり考えるものである。
「内省や判断、特別な熟練を必要とする」「ゆっくり伝わる情報」が関係してくる。
ダニエル・カーネマンが著書の中で指摘している。
認識は心の作業である。
他の作業と同様に難しくなると、私たちは怠けようとする
知性ある人でも、1つの答えを見つけると、それで満足してしまい、それ以上考えることをやめてしまう。
一方で、システム2の思考を必要とする活動では、自己抑制が必要であり、その抑制を継続することは楽しいことではない。
シェーン・フレデリック准教授は、知性の高い人が、システム1とシステム2との間をどのように進んでいくかを教えてくれる。
高学歴の大学生を集めて行われた実験。
いくつかの質問を出すが、その半数が間違えたのである。
質問① バットとボールの費用は、1.10ドル。バットは、ボールより1ドル高い。ボールの値段は?
質問② ある装置を5個作るのに、5台の機械で5分かかります。100台の機械で100個の装置をつくるのに、何分かかる?
質問③ 湖の中で、ユリが生えている区画がある。毎日その区画は、2倍になります。湖全体を覆ってしまうのに、48日かかるとすると、湖を半分覆うのに何日必要か?

「考えるのが面倒」って分かりますよね・・・
フレデリックは2つの大きなポイントを指摘する
- 最初によさそうな答えがパっと浮かぶと、システム2で苦労したくないから、とびつく
- システム2は、システム1の出した間違った答えを修正することが苦手
つまり、システム1の考え方にとどまり、システム2に移ろうとはしなかったのだ。
投資においては、システム1とシステム2はどのように機能するのだろうか?
- 投資家が、株式を買おうとしている
- システム1を使って、企業のPER、簿価、配当利回りを表に書き出す
- 投資家は、高い価値があると『即座』に判断する
このように、システム1だけで意思決定を行い、システム2で考えようとしない投資家が多いのだ。
ほとんど即座に自動的に行われる直感勝負である。
システム2は、システム1とは全く異なる。
システム2は、「別々の心」とも言われるほどだ。
システム2を動かすことのできる投資家は、企業の比較優位性や経営者の強み強みなど、企業の価値を生む要素について深く理解する。
しかも、バカげた意思決定を行わないように心理学の教訓が身についている投資家だけである。
システム2で、物を考える人は、努力と集中が要求されるため、忍耐強くなる。
バフェット流の原則は、システム1ではなく、システム2のゆっくり考えるものである。
5. マインドウェア・ギャップ

理性障害の2つ目の原因は、心の作業のための道具が不足することである。
システム2の内容が乏しいことを指し、「マインドウェア・ギャップ」と呼ばれる。
理性障害 1つ目の原因は「情報処理の問題」 2.合理性とは何か を参照
マインドウェアとは、心の作業をするための道具である。
マインドウェアによって、人は批判的かつ創造的に考える能力が高まる。
システム2を活性化するための必要な心の作業のための道具(マインドウェア)はどんなものだろうか?
- 対象企業、ライバル企業の決算書
- おおまかな企業価値の試算
- 経営者の質
- 友人、仕事仲間に、対象企業やライバル企業について相談する
これらの1つ1つの作業に、高い知性は必要はない。
しかし、単にその企業の現在のPERを調べるよりもはるかに手間がかかり、メンタル的にも努力と集中を要する。
6. 時間と忍耐

投資で成功するためには、忍耐強く長期的に考えることが最高であることは、多くの証拠が示すところである。
1960年代ニューヨーク、アメリカン証券取引所の回転率は10%以下。
しかし、現在では、回転率は300%を超える。
回転率とは
売買回転率のこと。
株式相場の活発さを示す指標のひとつ。
一般的には、回転率が高いほど売買が活発で、値動きが大きい傾向があります。
理論的には、市場の参加者が増え、取引量が増大すれば、より正しい価格が形成され、価格と価値のギャップは少なくなるはずである。
しかし、実際には、市場の参加者の大部分が投機を行っているため、全く逆の状況が生まれている。
バフェットが成功しているのは、異なるやり方で投資というゲームをしているからである。
時間と忍耐は同じコインの裏表であり、バフェットの根本である。
バフェットの成功は、完全子会社、保有株式のポートフェリオの両方において、静かにしかしずっと継続しているという忍耐強さの賜物である。
バフェットは言う
時間の最も魅力的なところは、それが長さをもっていること
理性と感情という重要な問題に戻ってみよう。
知性だけでは、投資での成功は約束されない。
投資家の脳の大きさよりも大事なのは、脳を感情から切り離す能力である。
バフェットの言葉を借りよう。
ほかの人々が短期的な欲と不安に基づいて意思決定をしているときには、合理的であることが不可欠だ。
その違いがお金を生み出す。
株式市場は、複雑な世界である。
合理性をなくした投資家は、
- 簡単にシステム1(直感)の思考にとらわれてしまう
- 欲と不安の感情に、とらわれてしまう
- 投資というゲームの中で、カモにされる
ポーカーでは、有名な格言がある。
しばらくゲームを続けていて、誰がカモか分からないときは、あなたがカモである
使ってみる

投資歴10年ほど。
「バフェットの法則」を読んで数年経ち、学んだことを実践しています。
意識して、実践していることを3つ挙げてみます。
- 「短期での投資は、勝率が悪い」を理解すること
- システム2を使うようにすること
- 投資経験を積むことを優先すること
【実践1】短期での投資は勝率が悪いを理解すること

短時間で伝わる情報は、大多数の人が評価するので間違いがない
短期での投機は以前より勝つことがむずかしくなり、リターンも小さい
要約からの引用。
まとめると、短期での投資は、
- 参加する人が、多い
- 多くの人が評価するので。情報の評価も正しい(から儲けるチャンスがない)
- 勝つことは以前より難しくなり、しかもリターンが少ない
「短期」とは真逆にある「長期」。
「長期投資の有効性」の説得力は、ずば抜けたバフェットの実績で十分と言えます。
バフェットは言います。
ほかの人々が短期的な欲と不安に基づいて意思決定をしているときには、合理的であることが不可欠だ。
その違いがお金を生み出す。
バフェットの言葉のように、多くの人が「欲」「不安」という感情で投資に臨んでいる。
「物事を合理的に考えることの有効性」もまた、並外れたバフェットの実績が、大きな説得力を持ちます。
「長期投資で臨む」「合理性を武器に戦う」ともに、多くの人と簡単に同調しない道をえらぶことになります。
まさに7章のテーマである「忍耐」が問われますよね。
【実践2】システム2を使うようにすること

システム2で、物を考える人は、努力と集中が要求されるため、忍耐強くなる。
バフェット流の原則は、システム1ではなく、システム2のゆっくり考えるものである。
「自分の頭は怠け者である」と常に意識するようにしています。
例えば、要約の中にもありましたこの問題。
見ただけで、考えたくないですよね。
質問① バットとボールの費用は、1.10ドル。バットは、ボールより1ドル高い。ボールの値段は?
質問② ある装置を5個作るのに、5台の機械で5分かかります。100台の機械で100個の装置をつくるのに、何分かかる?
質問③ 湖の中で、ユリが生えている区画がある。毎日その区画は、2倍になります。湖全体を覆ってしまうのに、48日かかるとすると、湖を半分覆うのに何日必要か?
投資で株を買う際、株を売る際も、
- 自分はシステム2を使って、しっかり考えた結果か?
- システム1が導き出す、安易な答えに飛びついていないか?
- この意思決定は、本当に正しいのか?その根拠は?
行動する前に、今一度自分自身に問いかけて、無理やりにでも「システム2」を動かすようにしています。
ただ、考えすぎて身動きが取れなくなることもあるので、ほどほどにはしています。
例えば、いろいろ考えすぎて、こんな経験があります。
- 必要以上に企業の悪いところが、目に入りすぎてしまう
- その企業のいいところすらも、だんだん不安になってくる
- 「だんだん考えるのが面倒になる」「損したくない」→「買う」「売る」ことを中止する
小さいことにこだわりすぎてしまうことを、『木を見て森を見ず』って言われますが、まさにそんな感じですよね。
参考になるのは、ハワード・マークスさんの著書「投資で一番大切な20の教え 賢い投資家になるための隠れた常識」
著書で述べられている「二次的思考」の話からです。
「二次的思考」とは、多くの人が考えることから、さらにもう一歩踏み込んで深く考えてみることです。
マークスさんの言葉を引用した方が分かりやすいですね。
(一次的思考からさらに)より鋭敏な思考である。私はこれを二次的思考と呼んでいる。
~中略~
二次的思考をする場合、脳にかかる負担は一次的思考よりも著しく大きくなる。
そして、一次的思考ができる人と違い、二次的思考ができる人の数はわずかである。
一次的思考をする人は単純な方程式や安易な答えを求める。
一方、二次的思考をする人は、投資で成功することは単純さの対極にあると分かっている。
引用 『投資で一番大切な20の教え 賢い投資家になるための隠れた常識』 1.二次的思考をめぐらす / ハワード・マークス 著
表現が違うだけで、考え方は「システム2を使う」と同じですね。
「投資で一番大切な20の教え」は、バフェットも認めた投資本の名著!
「二次的思考」も要約してみました。
ご興味がございましたら、ご覧ください。
-

【要約】投資で一番大切な20の教え 第1章 二次的思考をめぐらす
この記事は、「投資で一番大切な20の教え」という本の要約記事となります。 内容は、「はじめに」「第1章 二次的思考をめぐらす」となります。 本章の結論は、「他の投資家より、深く物事を考えて投資をしよう ...
続きを見る
【実践3】投資経験を積むことを優先すること

投資での忍耐は、投資家にとって市場の上げ下げが、どれほどのインパクトを与えるかを実際に経験してみることが一番成長につながります。
- 上がり続ける株価を見て、「もっと儲けたい!」と強欲に支配される
- 下がり続ける株価を見て、恐怖で足がすくんでしまう
- メンタルが、少しづつ強くなっていく実感(相場に振り回されない自信)
これらは、投資本をいくら山ほど読んでも、学ぶことができないからです。
例えば、投資歴10年の私。
初心者のころに比べれば、相当落ち着いて行動できるようになりました。(まだまだではありますが)
市場が引き起こす頻繁で気まぐれな株価の上下は、大きいもの、小さいものまでさまざま。
それらを何度も経験していくことで、「場慣れ」し「メンタルが強くなった」と実感しています。
「大損するかもしれない」とみんながパニックで逃げだしている時に、グッと踏みとどまる。(勇気をもって株を買う)
「株を買わなきゃ損」とみんなが欲に駆られて大騒ぎしている時も、グッと我慢する。
バフェットの言葉を借りると、
他人が貪欲になっている時は恐る恐る、周りが怖がっている時は貪欲に
引用 『1分間バフェット』 著 桑原晃弥 出版 SBクリエイティブ
さらに、レミング・ファクターが働きます。
「レミング・ファクター」とは、理屈に合っているかどうかに関係なく、ほかのみんながやっていることに従いたくなるという誘惑のこと。
引用 バフェットの法則 第6章 「レミング・ファクター」より
バフェットはこんな風に言います。
No.84 株を買うとき、私はレミングの集団移動の逆張りをする
引用 『バフェットの教訓』 メアリー・バフェット デビッド・クラーク 著 出版 徳間書店

本当は自分だけが、間違っているのではないか?
みんなに同調して楽になりたい・・・

自分の心の中のさまざまな心の葛藤や誘惑、感情と戦うことになります。
しかも忍耐を試される戦いは、精神的に相当ハード。
1人で考えることが怖いからと投資のプロの意見を真に受けて、安易に便乗することもできません。
なぜなら、投資のプロによる予想も毎回当たるわけではないからです。
結構な確率で、プロですら間違えています。
例えば、コロナ。
コロナが市場や経済に、ここまで大打撃を与えると予想できた投資のプロは、ほとんどいませんでした。
少なくとも私は、コロナが流行る前に、大声で警鐘を鳴らしていた投資のプロは知らない。
バフェットがよくいいます。「自分の頭で考えよ」と。
独力で考えることを心がけなさい。
いつも見ていて不思議に感じるのは、IQの高い連中が見境もなく人まねしている姿だ。
私の場合、他人と話していてよいアイディアが浮かんだことはことなど一度もない。
引用 ウォーレン・バフェット / 『バフェットの教訓』 メアリー・バフェット デビッド・クラーク 著 出版 徳間書店
投資における忍耐を鍛えるという意味では、「個別株投資」「インデックス投資」も同様です。
「個別株投資」では、気まぐれな市場の上げ下げによる忍耐を試されます。
「インデックス投資」は、どんなことがあっても、何十年もずっと継続して投資し続ける忍耐を試されます。
「インデックス投資」は、よく聞く失敗は、以下のようです。
- 何十年も、同じ方針を続けることが、我慢できない
- 飽きたりして、途中でやめてしまう
- 「動かないこと」に我慢ができず、株を買ったりなど余計な動きをする
「インデックス投資の生みの親」ジョン・C・ボーグル。
著書「インデックス投資は勝者のゲーム」で、インデックス投資で成功するために以下のことを主張しています。
ポイント
市場全体のポートフィリオを有するファンド(インデックスファンド)を取得し、永遠に持ち続けること!
最初に決めた方針を何十年も(ボーグルは永遠)貫き通すことを要求する「インデックス投資」は、恐ろしいほど投資家に「忍耐」を強いてきます。
結論としては、どのようなスタイルの投資であっても、投資を退場せず、長く投資経験を積むことで忍耐力が鍛えられます。
まとめ

いかがでしょうか?
まとめてみます。
本章で1番言いたいことは、以下の点です。
ポイント
投資で成功するためには、忍耐強く長期的に考えることが最高であることは、多くの証拠が示すところである。
投資に必要な忍耐力 7章要約
一般的に短い時間軸で行われる活動は投機的であり、長い時間軸で行われるものは投資と考えられる。
1. 長期間が大事
長期期間で投資を行うことは、本当に大きなリターンを得ることができるのか?
さまざまな調査の結果、長期投資を行うと大きなリターンを得られることに、議論の余地はなかった。
わたしたちの調査によれば、市場を大きく上回る差額を手に入れるチャンスは3年間保有したあとに最大になる。
2. 合理性とは何か
合理主義とは、意見や行動が感情ではなく、理性と知識に基づいて行われるべきだという信念や考え方のこと
知能指数やSATなどのテストは合理的な思考の測定にはほとんど役に立たない
3. ゆっくり伝わる情報
情報には2種類ある。
1. 直接的で内容が明白な情報(短時間で広く伝わる)
2. 評価するためによく考え、判断能力と熟練が必要な情報(伝わり方もゆっくり)
ゆっくり伝わる情報は、頭で理解することは難しいわけではない。
単純明快で明白な情報に頼るよりも労力を要する。
4. システム1とシステム2
人の認識は2つに分けられる。
「システム1」「システム2」と呼んでおり、特徴は以下の通りである。
| システム1 | 素早く連想させるもの(直感) |
| システム2 | ゆっくりした、ルールによって管理されたもの(熟考) |
システム1は、時間がかからず、細かい計算をするような知性を使わない。
システム2は、じっくり考えるものである。
システム2で、物を考える人は、努力と集中が要求されるため、忍耐強くなる。
バフェット流の原則は、システム1ではなく、システム2のゆっくり考えるものである。
5. マインドウェア・ギャップ
心の作業のための道具が不足することを、「マインドウェア・ギャップ」と呼ぶ。
マインドウェアを働かすことは、単にその企業の現在のPERを調べるよりもはるかに手間がかかり、メンタル的にも努力と集中を要する。
6. 時間と忍耐
投資で成功するためには、忍耐強く長期的に考えることが最高であることは、多くの証拠が示すところである。
バフェットは言う。
ほかの人々が短期的な欲と不安に基づいて意思決定をしているときには、合理的であることが不可欠だ。
その違いがお金を生み出す。
合理性を無くした投資家は、
・ 簡単にシステム1(直感)の思考にとらわれてしまう
・ 欲と不安の感情にとらわれてしまう
・ 投資というゲームの中でカモにされる
使ってみる
やっていること
・ 短期での投資は勝率が悪いを理解すること
・ システム2を使うようにすること
・ 投資経験を積むことを優先すること
続きは第8章へ
第8章は、『バフェットの法則』の全まとめとなります。
第1章から第7章までのバフェットの教えをギュッと詰まった内容です。
-

【まとめ】バフェットの法則(バフェットの法則8章要約)
この記事では、ウォーレン・バフェットの投資術を解説した本、『バフェットの法則』を紹介します。 内容としては、「第8章 なぜバフェットだけが偉大な投資家になれたのか」を要約した記事となります。 この記事 ...
続きを見る
よろしければ、ご参考までに。


